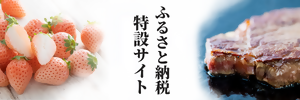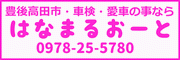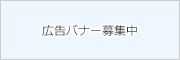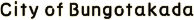本文
約300年の時を経て~富貴寺本堂大規模保存修理の公開・説明会開催
令和6年12月7日、富貴寺本堂の保存修理工事の現場公開と見学(説明)会が開催されました。
富貴寺本堂は、江戸時代中期(1715年)に建立されたと考えられる歴史的建造物で、国史跡「富貴寺境内」を構成する重要な要素として、平成30年度から全解体による保存修理が行われています。
この保存修理は建立以来(約300年経過)の初めての大規模な修理で、これまで部材の分解、木部の補修、基礎工事などが終わり、現在は柱や梁、屋根の叉首(さす)など建立当初の姿に復元、整備する組み立て作業が進められています。

※写真は、工事着手前の本堂(平成31年頃)です。屋根は「瓦ぶき」でしたが、今回の工事では、表面を銅板で覆い、かつての「茅(かや)ぶき型」の屋根に復元される予定です。
この日は、工事の設計監理を担当する(公財)文化財建造物保存技術協会の前堀勝紀さんから、文化財建造物の復元方法や、建立当時に使われていた大工道具、使用される木材などの説明があり、鉋(かんな)でヒノキを削る体験なども行われました。
文化財建造物の保存修理は、建立当時の木材を極力再利用し、建立当時の建築技術はもちろん、使用する材料も同じものを用いるとされ、工事現場では、埋木(うめぎ)や継木(つぎき)などの古い木材を保存するための補修技術なども間近で見ることができました。
また、今回のような大規模な修理は100年~150年に一度行われるとのことで、現在組み立てられている叉首の部分は、屋根が完成すると、次回の修理まで人目にふれることはないそうです。
未来へと伝統的な建築技術が引き継がれる富貴寺本堂の100年後の姿に、思いを馳せる参加者の様子がうかがえました。
富貴寺本堂の保存修理は、令和8年度末に完了する予定です。
■令和元年6月に行われた富貴寺本堂保存修理工事(分解工事)の見学会の様子も併せてご覧ください。
▶一般の方にも「富貴寺本堂」の文化財修理現場を公開しました!
▶一生に一度の体験!! 300年前の材料に学ぶ 「富貴寺本堂保存修理工事見学会(小中学生対象)」
■富貴寺本堂保存修理工事現場解説資料 [PDFファイル/954KB]
ケーブルテレビで放送します
今回取材した様子を市民チャンネル『週刊ニュース』で放送します。
ぜひご覧ください♪
放送期間:令和6年12月11日(水曜日)~12月17日(火曜日)
※放送日時は、予告なく変更する場合があります。
豊後高田市LINE公式アカウントのご案内
豊後高田市の出来事などを随時発信しています。
友だち登録は下記バナーをタップしてください。
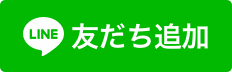 <外部リンク>
<外部リンク>