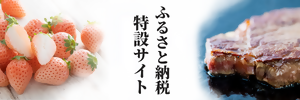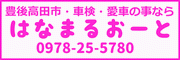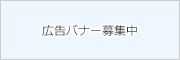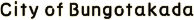本文
認知症への理解を深め「共に生きる」社会へ~家族支援プログラム公開講座~
令和元年7月9日、市と公益社団法人「認知症の人と家族の会大分県支部」の共催で、家族支援プログラム公開講座「介護体験者による認知症の講演会」を市役所高田庁舎で開催し、約200人が参加しました。
家族支援プログラムとは、認知症の方を介護している家族や認知症について詳しく学びたい方を対象に、(1)認知症について正しく理解する、(2)介護を上手に切り抜けるための仲間づくり、(3)認知症サポーターとなる、ことを目的とした学習と交流の場です。
この公開講座を皮切りに、12月まで毎月1回・計6回の講座を予定しています。
公開講座では、主催者を代表して、認知症の人と家族の会の中野洋子世話人代表が「本会では、電話相談や「家族のつどい」等で、実際に認知症の介護を体験した人が相談者の心に寄り添う活動をしています。本日の講座で認知症をさらに深く理解し、適切な対応を学べる機会となることを願っています」とあいさつしました。
講演では、認知症の母親を介護する伊藤啓子さん(中津市)が、徐々に母親の異変を感じ、認知症と診断されるまでの様子やグループホームに入ってからの生活等、様々なエピソードを交えて講演。自身の体験から「介護の辛さは、支援制度を上手に活用することで、減らすことができます。ぜひ積極的に利用してください」と呼びかけました。
また、急きょ認知症の義母を引き取り、4か月介護をした後藤清美さん(臼杵市)は、外部の支援を受けられないまま極限状態に陥った体験を講演。「1人で抱え込まない、相談できる人とつながっておく、介護制度について知っておく、ということはとても大切です」と話しました。
身近な病気「認知症」正しい知識と適切な対応を
2025年には、65歳以上の5人に1人が認知症またはその予備軍になると言われています。
市では、そうした課題に対応するため、「家族支援プログラム」の実施や地域の会合やサロンなどの開催にあわせて「認知症サポーター養成講座」を開催し、幅広い世代の方々に認知症に対する認識を深める機会を創出しています。
認知症サポーター養成講座
認知症サポーターとは、「認知症について正しく理解し、住んでいる地域や職場等で、認知症の人やそのご家族を温かく見守る応援者」のことです。
ご希望に応じて開催できますので、社会福祉課までお気軽にお問い合わせください。
認知症かも・・・と思ったら
認知症おたすけナビ[PDFファイル/8.73MB]
ご家族の方、地域の方が「認知症かもしれない」あるいは、「症状が進んでいる」と感じた時、認知症の状態に応じてどこへ相談し、どのような
ケアやサービスが受けられるかをとりまとめたものです。
適切なケア、サービスを受けることで認知症になっても自分らしく生活していくことができます。

行方不明に備えて
高齢者等SOSネットワーク
認知症等により高齢者の行方不明が発生した際に、市、警察署、協力機関等が連携して早期発見・保護する仕組みです。
ご本人の身体的特徴やかかりつけ医、緊急連絡先等の情報を事前に登録し、行方不明になった際に迅速な捜索活動を行うために活用します。