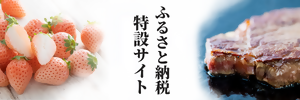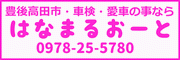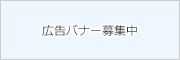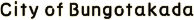本文
自転車活用の推進
目次
自転車の活用について
なぜ自転車なのか?国の動き
自転車はコミュニケーションツール
豊後高田市における自転車の活用
自転車の交通安全対策
自転車安全利用五則
関連のページ(リンク)国、県の計画など
自転車の活用について
環境、健康への関心の高まり、観光など地域経済活性化への寄与などから、自転車の活用が注目されています。
豊後高田市では、観光振興、地域経済活性化の活用はもちろんですが、環境負荷の軽減、健康寿命の延伸など、市政の目標達成のための手段としても、自転車の活用を検討していきます。
そこで、自転車の活用について、皆さんに知っていただくため、各種情報をお伝えしていきます。
※道路交通法の改正により令和5年4月1日からヘルメット着用が努力義務化されました。
なぜ自転車なのか?国の動き
国は、次のような基本理念により、自転車の活用を総合的・計画的に推進するため、「自転車活用推進法」を定めました。
自転車の活用を推進することにより、観光、健康、環境などの分野にも寄与するという考えです。
基本理念
- 自転車は、二酸化炭素等を発生せず、災害時において機動的
- 自動車依存の低減により、健康増進・交通混雑の緩和等、経済的・社会的な効果
- 交通体系における自転車による交通の役割の拡大
- 交通安全の確保
国の動き
平成28年12月 自転車活用推進法の公布
平成29年3月 「自転車の活用の推進に関する業務の基本方針について」閣議決定
平成29年5月 自転車活用推進法の施行
平成30年6月 「自転車活用推進計画」閣議決定
令和3年5月 「第2次自転車活用推進計画」閣議決定
この計画に4つの目標が掲げられています。
「自転車交通の役割拡大による良好な都市環境の形成」
「サイクルスポーツの振興等による活力ある健康長寿社会の実現」
「サイクルツーリズムの推進による観光立国の実現」
「自転車事故のない安全で安心な社会の実現」
自転車はコミュニケーションツール
大分県自転車活用推進計画2022より
「自転車は環境にやさしい交通手段であるとともに、サイクリングを通じた健康づくりや余暇の充実等、人々の行動を広げ、地域とのふれあいや仲間とのつながりを取り持つコミュニケーションツールでもあります。」
豊後高田市における自転車の活用
国東半島の独特な自然や地形、昭和の町、六郷満山、恋叶ロードなど豊富な観光資源を生かした自転車活用の取組が進められています。
レンタサイクル(観光地をめぐるツールとして活用)
仁王輪道(におうりんどう)
国東半島の4市町で取り組むサイクルルート。
平成31年3月からコースの紹介を始めました。
コースの魅力(仁王輪道HPから)
国東半島の観光資源は杵築市・日出町の風情のある城下町、豊後高田市の昭和の町など中心市街地のみならず、半島外周のリアス式の海岸線や世界農業遺産にも選ばれた里山エリアにも魅力が満載です。
山岳信仰の伝統が残る神社仏閣、良質な温泉などが数キロおきに点在していることは国内サイクルルートの中でも特徴的です。
山から谷、そして海岸線へと続く独特な地形は、バリエーション豊かなルートを生み出しました。
起伏に富んだ各ルートは、ペダルを踏み込む激坂や、絶景スポットが織り交ざり、ビギナーから健脚の方まで楽しめる内容になっています。
レンタサイクルも複数拠点で提供されています。
自転車の交通安全対策
昨今の自転車事故の現状を踏まえますと、交通安全、交通ルールの順守、自転車マナーの向上の取組も重要です。
【引用】国土交通省自転車活用推進本部資料「自転車事故の損害賠償に係る現状について」から抜粋
対歩行者との事故の場合、自転車側に責任割合が多くなり、賠償額の負担が大きくなる点が問題となる。
歩道上での自転車と歩行者の事故の場合、自転車側が基本100%の責任となる。
自転車安全利用五則
(令和4年11月1日から)
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先<外部リンク>
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認<外部リンク>
- 夜間はライトを点灯<外部リンク>
- 飲酒運転は禁止<外部リンク>
- ヘルメットを着用<外部リンク>
乗車前の点検も、確実に行いましょう
点検の合い言葉は"ぶたはしゃべる"(一般社団法人自転車協会HP)<外部リンク>
「ぶ」ブレーキ
「た」タイヤ
「は」反射材(リフレクタ)
「しゃ」車体(ハンドル、サドル、チェーン)
「べる」ベル
2020年7月2日自転車に関する注意喚起について(依頼)(大分県HP)<外部リンク>
2020年6月24日自転車に関する消費者事故等の傾向について-乗車前の点検を確実に行いましょう!(消費者庁HP)<外部リンク>
自転車損害賠償責任保険等への加入
自転車を利用中の事故で、他人にけがをさせてしまった場合など、相手の生命、財産の損害を補償できる保険の加入。
大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(大分県HP)<外部リンク>
施行期日:令和3年4月1日(保険加入の義務規定は令和3年6月1日)
他の移動手段との組合せも重要です
すべて自転車の活用に切り替えるということではありません。例えば、移動手段として、目的地までは自動車が最適という場合もあります。
そして、目的地に着いてからその周辺の移動は自転車が最適という場合もあり、複数の移動手段で、効率的な移動が可能になります。
よって、自動車-自転車、公共交通機関-自転車、徒歩-自転車など、自転車の活用が最も考えられる場面で自転車の活用を推進していくことになります。その際は、自転車の活用にうまくつながるように、(停めて移動する。乗せて移動することなどを想定し)自転車を活用する前後の環境を改善していくことも、重要になります。
関連のページ(リンク)
国・県の計画など
自転車の日(5月5日)、自転車月間(5月)<外部リンク>
自転車活用推進法では、5月5日を「自転車の日」、5月を「自転車月間」と定めています。
自転車活用推進本部(国土交通省HP内)<外部リンク>
ナショナルサイクルルート | Good Cycle Japan(国土交通省HP内)<外部リンク>
大分県自転車活用推進計画2022(大分県HP内)<外部リンク>
大分県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(大分県HP)<外部リンク>
公布:令和2年12月
施行期日:令和3年4月1日(令和5年4月1日改正)
大分県内のサイクルルート関連
サイクリングおおいた(大分県HP内)<外部リンク>
仁王輪道(におうりんどう)<外部リンク>
豊後高田市ほか国東半島の4市町で進める国東半島のサイクルルートです。
別府湾岸・国東半島海べの道(日本風景街道)<外部リンク>
九州・山口サイクルマップ(大分県HP内)<外部リンク>
環境・健康対策関連
ストップ地球温暖化 大分県ノーマイカーウィーク(大分県HP内)<外部リンク>
健康アプリ「おおいた歩得」のサイクルイベントについて(大分県HP内)<外部リンク>
自転車の普及関連・その他
日本自転車普及協会<外部リンク>
Tabirin(たびりん)<外部リンク>
一般社団法人自転車協会<外部リンク>