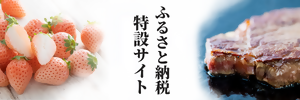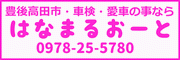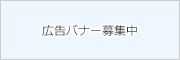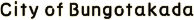本文
国民健康保険税の軽減について
低所得世帯の軽減について
国民健康保険税の算定において、世帯主(擬制世帯主を含む)及びその世帯に属する加入者(被保険者)の総所得金額等の合計額が、次の表の基準以下となる場合に均等割及び平等割が軽減されます。
※令和7年度賦課分から軽減対象範囲が広がりました。
|
軽減割合 |
世帯の所得合計額 |
|---|---|
|
7割軽減 |
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
|
5割軽減 |
43万円+(30.5万円×国保被保険数と特定同一世帯所属者数の合計数)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
|
2割軽減 |
43万円+(56万円×国保被保険者数と特定同一世帯所属者数の合計数)+10万円×(年金・給与所得者数-1)以下 |
|
注意事項
|
|
※世帯主及び国保被保険者等のうち、所得の未申告者がいる場合は、低所得世帯の軽減を受けることができません。所得の有無にかかわらず、毎年必ず所得申告をしてください。
※令和4年度より、軽減対象世帯のうち、未就学児に係る医療分・支援分の均等割額の軽減割合が以下のとおり変更されました。(令和3年度以前については、従前から変更はありません。)
軽減:7割→8.5割、5割→7.5割、2割→6割、軽減なし→5割
後期高齢者医療制度への移行に伴う緩和措置
後期高齢者医療保険に移行することによって、国民健康保険加入世帯の負担が大きく変わることのないように、次のような緩和措置を行っています。
1.平等割の軽減
後期高齢者医療保険への移行者が生じたことにより、国民健康保険加入者が1人となる世帯について、医療分と支援分の平等割が軽減されます。緩和措置期間は8年間で、最初の5年間は2分の1、続く3年間は4分の1が減額されます。ただし、期間中に他の世帯員の方が国民健康保険に加入した場合等は終了します。
2.旧被扶養者の減免(平成31年度賦課分から変更されました)
被用者保険(会社の健康保険等)から後期高齢者医療保険に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の加入者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については次のような減免が受けられます。
- 所得割が免除になります。
- 7割・5割軽減に該当しない場合は、均等割が半額になります。(資格取得後2年を経過する月までの間に限ります)
- 旧被扶養者のみの世帯で、7割・5割軽減に該当しない場合は、平等割が半額になります。(資格取得後2年を経過する月までの間に限ります)
非自発的失業者に係る国民健康保険税の軽減措置
倒産・解雇・雇止めなどの理由で離職された方(非自発的失業者)が、安心して医療にかかれるように、国民健康保険税の負担を軽減します。
対象者
「雇用保険受給資格者証」により、1、2に該当する方。
- 離職理由コードが「11・12・21・22・23・31・32・33・34」の方
- 離職年月日が平成21年3月31日以降の方
※「雇用保険受給資格者証」が交付されていない場合は対象になりません。
※「特例受給資格者証」(短期雇用特例被保険者)及び「高年齢受給資格者証」(失業時点の年齢が65歳
以上)を交付されている場合は対象になりません。
軽減の対象となる期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで
保険税の軽減方法
失業した本人の前年の給与所得を30/100とみなして国民健康保険税を算定します。
申請方法
申請には雇用保険受給資格者証、保険証が必要です。
保険年金課・地域総務一課・地域総務二課で申請の手続きができます。
産前産後期間の軽減措置
出産を予定されている、または出産された被保険者の産前産後期間中に係る国民健康保険税を軽減します。
対象者
国民健康保険加入者の方で、令和5年11月1日以降に出産予定または出産(※)された方
※妊娠85日(4ヵ月)以上の出産(死産、流産、早産を含む)
軽減の対象となる期間
| 単胎妊娠の場合 | 出産予定月または出産月の前月から出産2ヵ月後の4ヵ月間 |
|---|---|
| 多胎妊娠(双子以上)の場合 | 出産予定月または出産月の3ヵ月前から出産2ヵ月後の6ヵ月間 |
軽減内容
令和6年1月以降の対象となる期間の国民健康保険税の所得割と均等割を減額します。
※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の国民健康保険税が減額されます。
※令和6年1月より前の期間については減額の対象になりません。