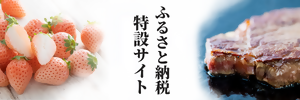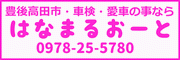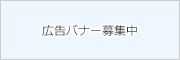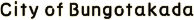本文
「昭和の町は教育のまちです」事業
1 趣旨
本市は「千年のロマンと自然が奏でる交流と文化のまち」づくりを将来の都市像として、数多くの施策を推し進めているところである。その中心的核として15年目を迎えた「昭和の町」や観光施設の果たしてきた役割は大きく、「昭和の町」を取り巻く商店街や観光エリアはさらに活性化され、一段と進展を見せている。
これまでの多様な取組における「ひと」「もの」「こと」づくりを通しての「まちづくり」の大きな原動力はやはり、「ひとづくり」であると考え、昭和の時代に活気溢れる地域力や教育力の有り様に学び、現在の取組を見直すことで、新たな生きる力と豊かな心をそなえもつ「豊後高田っ子」の育成を図る。
2 事業内容
(1)昭和30年代の学校教育の良さを発見・発掘し、実践する取組
- 当時の教育資料を紐解きながら教育課程をもとにした教材や教具の掘り起こしを行う。
- 当時の子どもを取り巻く環境の分析を行い、「生きる力」のとらえ方を見つめ直す。
- 市職員や教職員の若い世代の考えを取り入れるためにプロジェクトチームを立ち上げ、次世代の教育に必要な「子ども像」や「地域像」「学校像」「教師像」を発掘・創造する。
(2)「学びの21世紀塾」事業の充実
- 寺子屋講座の充実を図る。
- テレビ寺子屋講座の活用の充実を図る。
- 寺子屋昭和館、寺子屋プラチナ館、寺子屋戴星堂の活用の充実を図る。
- 受講生のニーズに沿った事業内容を行う。
(3)伝統文化の継承
- 真玉歌舞伎や岬・西叡太鼓、夷里神楽等の伝統文化を継承するための環境整備(人的・物的)を図るとともに発表の機会を設ける。
- 地域にある伝統文化を発掘し、地域おこしの一役を担う。
(4)豊後高田市学力定着状況調査事業の取組
- 市単独の調査を実施し、全国、県の状況調査と合わせて、児童生徒の学力の向上を図る。
- 実施学年、実施時期、実施内容等の検討をする。
- 課題を共有のものとする連絡会議を実働化させる。
(5)保幼小中高連携の積極的な取組
- 保幼・小との連携を深め、「小1プロブレム」の解消を図る。
- 小学校と中学校が子どもの実態に即したさらなる連携を図ることで、心的不安を取り除き「中1ギャップ」の解消を図る。
- 自ら学ぼうとする「アクティブラーニング」の取組を小中連携のもと再構築する。
- 小小、小中、中高による授業公開を通して教師の指導力の向上を図る。
(6)公立幼稚園の充実
- 人間形成の基礎を培う幼児期の子どもに、人とのかかわりを通しての「学ぶ力」や「豊かな感性」を育む。
- 「市幼児教育振興プログラム」を作成し、幼児教育の充実を図る。
(7)家庭教育力の充実
- 家庭教育力の充実を図るため、講演会や相談会を開催し、不安解消や家庭教育力の向上を図る。
- 家庭教育学級等の取組を継続して行えるよう、市PTA連合会との連携を図る。
(8)スポーツの振興
- 運動の機会を増やし、児童生徒の体力の向上を図る。
- スポーツ少年団活動や中学校部活動を活発化し、九州・全国大会に多くの児童生徒が参加できるよう指導体制の強化を図る。
(9)県外特別研修事業の有効的な活用
- 「変わる社会に、変わらなければならない学校~そして教職員の意識も~」のもと、先進地研修を行い、各学校での実践に生かす。
- 研修交流会を開催し、教師力向上を図る。